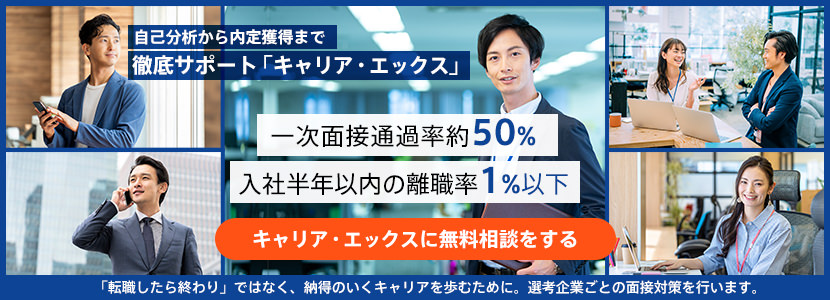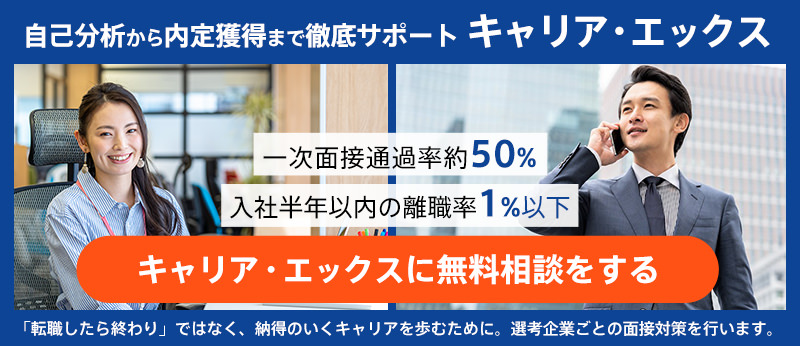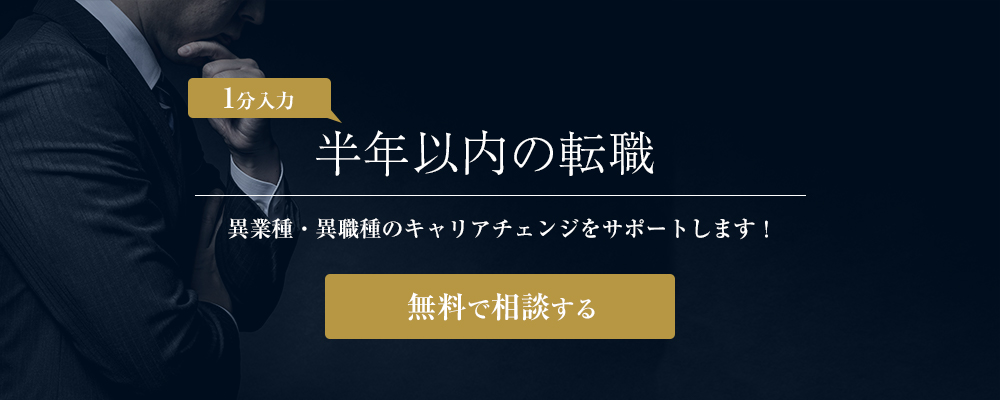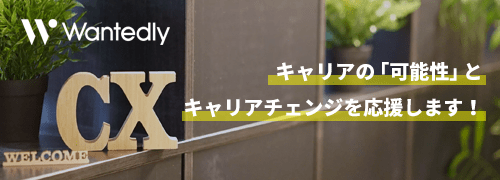設立して日が浅い会社のことを、「スタートアップ」「ベンチャー」などと呼びますが、両者の違いをご存じですか?
似たような意味で使われることが多いですが、実は2つには明確な違いがあります。
この記事では、スタートアップとベンチャーの違いを解説するとともに、どちらが向いているのか判断する際のポイントなどについて解説します。
スタートアップとベンチャーの基本的な違い
スタートアップとベンチャーは、いずれも設立して日が浅い、比較的新しい企業のことを指します。明確な定義はないものの、両者はビジネスモデルや成長スピードなどの点で、次のような違いがあります。
革新的なサービスで市場を創造するスタートアップ
スタートアップは、既存のビジネスモデルではなく、常識を覆すような全く新しいビジネスモデルを構築して、新たな市場を創造することを目指します。
一方、ベンチャーは既存のビジネスモデルをベースとしており、「ビジネスモデルに革新性があるかどうか」がベンチャーとの大きな違いとなっています。
例えば、フリマアプリを展開するメルカリは、革新的なアイディアとIT技術を用いて、個人間で商品の売買を行えるマーケットプレイスを生み出した、スタートアップの代表例です。ネットで印刷物を注文できるラクスルは、印刷業界にITを取り入れ、小規模印刷需要を獲得することで急成長しています。
なお、経済産業省では「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」を公開し、事例として紹介しています。
※経済産業省「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」
既存市場で成長を目指すベンチャー
一方ベンチャーは、既存のビジネスモデルをベースに独自の技術や工夫、アイディアなどで新たなビジネスを生み出している企業を指します。
大企業では取り組みにくいスモールビジネスが多く、持続的なイノベーションを目指しています。
組織文化から見る2つの違い
スタートアップとベンチャーは、どちらも設立して日が浅いため、フラットで柔軟性のある組織文化を持っているケースが多いです。経営陣の意思決定スピードが速く、承認や決済のプロセスもシンプルであることから、ビジネスの展開スピードも速いのが特徴です。
ただ、スタートアップのほうが、よりスピード感を重視し、経営の意思決定スピードが速い傾向にあります。
スタートアップは、短期間で成果を上げることを目指すため、アイディアを迅速に実行する必要があり、意思決定のスピードが速いのです。
今までにない新たなビジネスを展開することから、最小限の予算や人材リソースで必要最低限の機能を備えた製品やサービスを作り、市場の反応を見ながら改善する手法「リーンスタートアップ」を取り入れるケースも多いようです。
イノベーション重視vs市場シェア重視
スタートアップは、これまでにない新たなビジネスを投入し、市場を切り開く役割を担っています。ビジネスに対する認知も需要もない状態からスタートするため、イノベーションを追求し続け、社会に変革をもたらそうとするゆるぎない姿勢が重要視されます。
一方のベンチャーも、イノベーションが求められるものの、ベースは既存ビジネスであるため、持続的な成長が重視されます。
既存市場のなかで競合優位性を発揮し、市場シェアを獲得して成長を目指すことが求められます。
EXIT(出口)戦略の違い
EXIT(出口)戦略とは、ベンチャーやスタートアップが、出資者(投資家)に対して利益を確定させ、キャッシュ化する戦略のことを指します。
どのようなEXITを目指すのかによって資金調達方法も変わるため、設立段階からEXIT戦略を明確にしておくことが重要です。
スタートアップは、創業時に投資家からの資金調達を行うため、収益改修のためのEXIT戦略を明確に提示する必要があります。IPO(株式公開)やM&Aによる事業売却といったEXIT戦略を目標とするケースが目立ちます。
ベンチャーは、既存のビジネスモデルをベースに事業を長期的に拡大し続けることを目指すため、EXITまでの期間も比較的長めです。IPOによるEXITが多く、上場後も経営陣がそのまま経営を続けるケースも少なくありません。中には明確なEXIT戦略を定めないケースもあります。
スタートアップとベンチャー、資金調達の違いは?
スタートアップとベンチャーでは、資金調達方法にも違いがあります。
ベンチャーは既存のビジネスモデルをベースに、中長期的な成長を目指すため、設立間もない段階であっても一定の収益を確保できると期待されます。そのため多くの場合、銀行からの融資や助成金・補助金などを利用することが可能です。
一方のスタートアップは、今までにないビジネスモデルで市場を作ることから、どうしても倒産のリスクが伴います。
初期段階では知名度がなく、需要も見込めないことから、収益を確保できるまでにある程度の時間が必要となります。そのため、設立間もない段階では、リスクの高さから銀行融資を受けるのは難しいでしょう。
エンジェル投資家など、将来性や新規性、ビジネスモデルに着眼して出資を決める投資家や、日本政策金融公庫の創業融資、クラウドファンディングなどにより資金調達を行います。
スタートアップの成長ステージごとの資金調達方法
スタートアップにおいては、成長ステージごとに資金調達方法も変わっていきます。下表はおおよそのイメージとなります。
あなたに合うのは、スタートアップ?それともベンチャー?
ここまでスタートアップとベンチャーの違いについて説明してきましたが、実際に働くならどちらがいいのか、考え方のポイントについてご紹介します。
将来のキャリアプランから考える
スタートアップとベンチャーでは、得られる経験やキャリアが異なります。次のようなポイントで判断するといいでしょう。
●スタートアップに向いている人
スタートアップでは、思考錯誤を繰り返しながら今までにない新たな市場を切り開く力が求められます。新しい事業や商品・サービスを生み出したり、会社そのものの体制を整備したりするなど、0→1に関われるチャンスは多いでしょう。
・事業や商品・サービスの立ち上げなど0→1に関わりたい人
・新しい制度を考えるなど会社作りそのものに関わりたい人
・さまざまな業務経験を積んでキャリアの選択肢を広げたい人
・将来経営に関わりたい人
●ベンチャーに向いている人
ベンチャーは、既存ビジネスをもとに新たなビジネスを生み出し、成長を目指しています。ある程度、事業の方向性が定まっていることから、0→1経験は積みにくいですが、事業拡大のために現場で多くの経験を積むことができます。
現場でPDCAを回しながら自分の力で事業を動かし、拡大させる喜びを感じたい人は、ベンチャーのほうが向いているでしょう。
・現場経験を積みたい人
・自らの手で既存事業をスケールさせたい人
・高速でPDCAを回したい人
・会社の成長を肌で感じたい人
※関連リンク:【ベンチャー企業に転職する人必見】あなたに合ったベンチャー企業の選び方
スタートアップ参画のメリット
繰り返しになりますが、スタートアップに参画する最大のメリットは、まだ誰もチャレンジしたことのない市場に臨めることです。
フロンティア精神を持って市場を切り開き、0→1経験を積めるという点は、他の成長ステージでは味わえないメリットと言えます。
組織がまだ小さく、1人で何役もこなさなければならないことから、「自分の専門性を追求したい」人には向きませんが、さまざまな経験を積むことで引き出しが増え、将来の選択肢も拡大するでしょう。
そして、経営陣とごく近い場所で働くことになるため、経営者の働きぶりを間近で感じられる点も特徴です。経営者の意思決定のシーンに関わる場面も多く、自然と経営視点が養われるでしょう。
安定的に収益が得られるようになるまでは給与水準は低いと考えられますが、ストックオプションやRSU(譲渡制限付き株式ユニット)などを付与するスタートアップは多く、将来的に大きなリターンが得られる可能性もあります。
前述のように、先行きが読めない市場にチャレンジすることになるため、事業が成功するとは限らず、失敗・倒産リスクは少なからずありますが、得られる経験は非常に多く、ビジネスパーソンとして成長できる環境と言えるでしょう。
まとめ
前述のように、スタートアップとベンチャーにはビジネスモデルや成長スピード、収益性などで違いがあります。
働く環境や得られる経験も異なるため、転職の際には自分の希望や条件に合った成長ステージの企業を選ぶことが大切です。
一方で、成長ステージが浅い企業ほど求人件数も少なく、求人そのものを公開していないケースもあることから、転職したくてもなかなか募集を見つけられない可能性があります。
転職エージェントでは、スタートアップやベンチャーの非公開求人を保有しているところがあるため、転職を希望する人は活用してみるといいでしょう。
キャリア・エックスでは、今後の成長が期待できる有望なスタートアップの案件も数多く保有しており、転職支援実績も豊富です。各企業の内情にも精通しており、あまり表に出ていないスタートアップの情報も提供しています。
スタートアップやベンチャーに興味のある方は、ぜひキャリア・エックスの活用を検討してみてください。